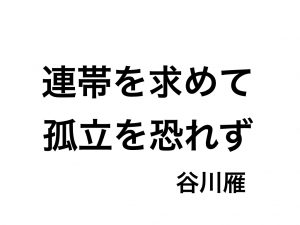全共闘のスローガン「連帯を求めて孤立を恐れず」の出典
今この時代で、ほとんど忘れられている存在となっている谷川雁のことが気になっている。
先日読んだ、松本輝夫「谷川雁 永久工作者の言霊」(平凡社新書)は、複雑で捉えにくい谷川雁の軌跡を明快に描き、非常に思うところ大であった。
かつての全共闘のスローガンとも言える「連帯を求めて孤立を恐れず」は、好きな言葉の一つである。しかしながら、その出典、もともと誰がどんな文脈で語った言葉なのかを、これまで私は知ろうとしてこなかった。
全共闘の文脈で語られるとき、この言葉には続きがあるらしい。
連帯を求めて孤立を恐れず、力及ばずして倒れることを辞さないが、力尽くさずして 挫けることを拒否する
この出どころは、東大全共闘が安田講堂に立てこもった際に、壁に書かれたものであるらしい。引用した先のページには画像もある。
私はいつもこの文章の後段、「力及ばずして〜」からの部分に違和感を覚えてきた。
前段の持つ高い思想性に対して、あまりに日常的かつ教条的な硬直化した文章が後段に接続されているように思えるのである。一つの文章でありながら、別々の上半身と下半身をつなぎ合わせたキメラのような座りの悪い文章。更に前段の思想性が後段の俗物性によって打ち消されている。
要するに、これを「力及ばずして〜」までの文章として真面目に捉えたとしたら、この文章は1人の人格から書かれたとは到底思えないのである。
前段の「連帯を求めて孤立を恐れず」自体が谷川雁によるものであることは、ほぼ確定であろう。
まずは、そこに拘ることとして、その文章が述べられた原典を探すことにした。
リファレンス情報などによると、この文章は、谷川雁の評論集「原点が存在する」の中の「工作者の死体に萌えるもの」に記載されていることがわかった(なお、実際の初出は1958年6月「文学」に掲載されたもの;評論集「原点が存在する」(現代思潮社版)の記述より)。
さっそく古本屋で入手した、評論集「原点が存在する」(現代思潮社版)から、実際の部分を引用してみることにする。
「連帯を求めて孤立を恐れず」は、まさにこの工作者(=社会主義運動の扇動者、オルガナイザーを指す)が、大衆を組織する方法論について論じている評論「工作者の死体に萌えるもの」の最終部分にあった。
大衆と知識人のどちらにもはげしく対立する工作者の群・・・・・・双頭の怪獣のような媒体を作らねばならぬ。彼等はどこからの援助を受ける見込みはない遊撃隊として、大衆の沈黙を内的に破壊し、知識人の翻訳法を拒否しなければならぬ。すなわち大衆に向かっては断乎たる知識人であり、知識人に対しては鋭い大衆であるところの偽善の道をつらぬく工作者のしかばねの上に萌えるものを、それだけを私は支持する。そして今日、連帯を求めて孤立を恐れないメディアたちの会話があるならば、それこそ明日のために死ぬ言葉であろう。
谷川雁「原点が存在する」(現代思潮社版)p.57
引用終わり
良い文章である。
そして後段の部分は明らかに第三者の付け足しであろう。
この文章を書いた頃の谷川は、炭鉱労働者の支援のため福岡県中間市に移住し、労働者の生活の中に入り、工作者として労働者の文化的サークルを水平的に組織する活動(「サークル村」)を組織しようとしていた。
この文章では、まさにその「大衆」=「労働者」の生活圏の中に入った「知識人」である「工作者」=谷川たちの姿勢を直截的に表明しているといえる。知識人=前衛という直線的な道筋ではなく、工作者のあり方として「知識人」でもなく、「大衆」でもなく、という矛盾に満ちた道筋が描かれる。
その道筋とは「偽善」に満ちたものであり、その言説は「明日死ぬ言葉」になる宿命を持つものだというのである。あるいは、コウモリのようなどっち付かずの裏切り者であり、居場所はどちらにもない。永続性すら断ち切られ、明日死ぬことが預言されている。
逆説と矛盾に満ちている。
しかし、こうした逆説と矛盾に満ちた場にこそ、工作者のメディア(媒体)が唯一存在する意味がある、という谷川雁の強烈な宣言となっているのである。
現実の双貌性=矛盾を武器とした「コピー」の恐るべき切れ味
谷川雁は、コピーライターとして抜群の文章力を持っている。「連帯を求めて孤立を恐れず」だけでなく、この文章が収められている論文のタイトル「工作者の死体に萌えるもの」も、この記事を執筆している2018年においても全く古びていないフレーズである。
また谷川雁は詩人でもあった。
彼の詩には、平易なようで、読者にとって容易な理解を拒む難解な面も多くある。
(前略)
つまづき こみあげる鉄道のはて
ほしよりもしずかな草刈場で
虚無のからすを追い払え
あさはこわれやすいがらすだから
東京へゆくな ふるさとを創れ
「東京へゆくな」(現代詩文庫 谷川雁詩集 p.26)
引用終わり
おれは大地の商人になろう
きのこを売ろう あくまでにがい茶を
色のひとつ足らぬ虹を
夕暮れにむずがゆくなる草を
わびしいたてがみを ひずめの青を
蜘蛛の巣を そいつらみんなで
狂った麦を買おう
古びておおきな共和国をひとつ
それがおれの不幸の全部なら
〔後略〕
「商人」(現代詩文庫 谷川雁詩集 p.18)
引用終わり
谷川は、逆説を用い、両義性のある言葉を使い、矛盾を以って現象を切断することを意図的に行なっている。単一の意味の解釈を拒否し、言葉の意味は対立し分散する。多義性すなわち矛盾を直視する。総じて、矛盾=現実の持つ双貌性をイメージによって打開する意思が強く表現されている。
先に引用した「連帯を求めて孤立を恐れず」を導き出す文章がまさしくそうであるように、こうした戦略を散りばめたイメージを意図的に読者の前に展開しているようだ。それがために、谷川が発した「言葉」の断片(散文ではなく)は、切れ味の鋭い活きた「コピー」として、現代でも価値を有する言葉となりえている。
俯瞰した視点で捉えると、創造する側の思考様式としては、これはいわゆる弁証法的唯物論の思想(否定の否定)の一形態である。弁証法的唯物論そのものが矛盾を扱う理論として、共産党員でもあった谷川自身も言わずもがなとして、当然理解しているはずであったであろう。
ただ、ここではさらにその部分に大衆の「生活」の視点を強く付加している点を指摘しておきたい。理論あるいは形式知とは相容れない部分としての日本固有の土着の匂いを強く感じるのである。
工作者=オルガナイザーの宿命ー他者の人生を変えること
松本輝夫「谷川雁 永久工作者の言霊」(平凡社新書)によれば、谷川雁の福岡県への移住、炭鉱労働者との共闘は結局失敗し、同志たちとも決別し、本人は逃亡さながらで東京に戻ってくることになる。
炭鉱産業自体がエネルギー革命によって縮小していく中で、「しんがり戦」を戦い、闘争の成果としては一定の形が整ったのちに、かつて一枚岩であった組織には「血縁集団」と「思想集団」(谷川は当然こちらに属していた)との分裂が起こったという(松本輝夫「谷川雁 永久工作者の言霊」p.114)。
著者の松本が1963年に谷川の福岡県の住居を訪ねた際のエピソードとして、柳田国男と折口信夫の著書が谷川の家にあったことを、驚きをもって記載している。
(前略)書棚をみると、柳田国男と折口信夫の本がやたらと目立っていたこと。(中略)
そこで、「谷川さんは、この二人の書いたものをもとに大正闘争に関わっているのですか」といった問いを発したこともまちがいない。そして「これらが闘争の武器となっているということは無論ないが、この二人の著作には炭鉱の若い者たちや女たちとつきあっていく上での知恵やヒントが無尽蔵にある。とくに柳田は参考になる」との返答をもらったことにまた度肝を抜かれた。
松本輝夫「谷川雁 永久工作者の言霊」p.15-16
引用終わり
こうした日本人の心性の基礎部分に、民俗学の知識までも積極的に用いたうえで周到に注意を払っていた谷川でさえも日本的社会構造=「血縁集団」の中で排除されてしまう現実。
工作者として他者の生活を変化させることはできなかった。
その結果は「失敗」と総括すべきであろう。
しかしながら、谷川雁のこれまでの言説を辿ってきた限りにおいて、その総括を単純な「敗北」として受容する必要はないのではないか、そうした心理が働くことを否定できないのである。
他者の人生を変えること、すなわち精神まで含めた生活の中で「人間を変化させること」の結末が、その集団からの自らの「排除」であったとしても、谷川にとって、その事実をほんとうの意味で「敗北」だと解釈して良いのであろうか。
谷川自身でさえもそれを「逃げた」と告白したにも関わらずである。
いわば「裏切り者」「偽善を貫く者」こそが、現実に存在する矛盾の解決のために必要であって、今日発せられ明日には死んでゆく言葉こそが工作者の本義と信じた谷川にとって、自分が否定され排除された事実を、その工作が他者に影響を与え変化を促した成果として正統に解釈することは許されることではなかろうか。
急いで付け加えると、それは意図して「偽善」を働き、対立概念の”どちらでもないもの”を介在して産まれた成果こそが時代を進めるための新たな付加価値を与え、それを生み出す契機を与えた自らは双方の立場から裏切者として断罪され否定される、という<生成のダイナミクス>を信じていたはずの谷川にだけ許される言説である。
こうした思いを抱くことは、谷川に肩入れしすぎであろうか。
終わりに 〜しかばねの上に萌えるもの
谷川雁が発した両義性豊かな「言葉」の断片はこうして、まだ生命力を保っている。
そして、その「生命」とはガラスの保存箱に入れられたような静止したものではなく、個々の生死を繰り返しつつ種として永続する植物のような動的な統一体に例えられるものである。
その”しかばね”は、単純な生を否定した形式ではない。その内部に次の生命の種を宿している。
こうした「しかばねの上に萌えるもの」が、今なお我々にメッセージ性を持って届いているということは、素直に驚嘆に値することであろう。
(文中敬称略)
参考文献:
谷川雁「原点が存在する」(現代思潮社)
谷川雁「現代詩文庫 谷川雁詩集」(思潮社)
松本輝夫「谷川雁 永久工作者の言霊」(平凡社新書)